意味
釈迦如来は如来の一種で、仏教の教祖ブッダ(シャカ)に強く関わる仏様です。
音写は釈迦牟尼。釈迦文や釈尊とも。密号は寂静金剛。
三昧耶形は鉢。袈裟・錫杖を加える解釈もあり。
釈迦如来=ブッダ?
釈迦如来はブッダか仏尊か、意見は分かれます。
あくまでも如来(仏様)の一つだと考えると、「釈迦」は、仏教の教祖である生身のブッダ(仏陀)と異なります。
とはいえ、ブッダが仏様になったと考えることもできますから、
こういう捉え方に大別されます。
次のようにみると、両方の説が活きてきます。
キャリア
不空成就如来と同体
不空成就如来と同体。
一切の無明煩悩を寂滅し、化仏事業が円満して空しくない意味。
天鼓雷音如来と同体(北方の釈迦)
釈迦を密教的に位置づけると、次のように考えられます。
- 天鼓雷音如来の役割…天鼓が形相も住処もなく、法音を演説して衆生を警悟(説法教化)
- 説法教化の働き…大寂静に住しながら、天鼓が自然に雷鳴
北方の月輪や花葉に表現されるため「北方の釈迦」といいます。
形姿

釈迦如来。土佐秀信画『仏像図彙』三、1900年、5丁。
「大日経疏」の説法印
身体は金色で光輝と三十二相を具え、白蓮華に坐して説法の相をしています。
左手は赤黒色の袈裟の角を執り、右手は指を立てて大指・無名指を相持。

臍前に両手を仰向けて重ねて、両方の大指を曲げて鉢を持つ鉢印パタンもあり。
ほかの説法印
説法印は智吉祥印ともいい、経典によってバラバラで、いくつもパタンがあります。
- 下化・上求の表示…左手を胸前に仰向け、右手を左手の上に覆う
- 報身説法印:大指・中指を捻ずる
- 法身説法印:大指・無名指を捻ずる
- 応身説法印:大指頭指を捻ずる
現図曼荼羅
印の結び方が「大日経疏」と異なります。
袈裟は同じく赤黒色で、右掌を胸の前に立て、左手も胸前に掌を内に向けて立て、両手とも中指・無名指を屈げています。
報身の釈迦(「陀羅尼集経」釈迦仏頂三昧陀羅尼品)
二獅子の戴く七宝華上に結跏趺坐しています。
- 右手:臂と掌を仰向けて右膝の上に置き、指頭は垂れて華上に至る相
- 左手:臂を曲げて掌を仰向けて臍の下に横たえる相
左右臂の上に各3個と頭に1個、七宝瓔珞を着用。頂上に七宝の天冠を頂きます。
このような宝冠・瓔珞を着ける釈迦を「報身の釈迦」といいます。
文化財
曼荼羅
密教では、釈迦を本尊とする別尊曼荼羅があります。
- 菩提場経曼荼羅
- 宝楼閣経曼荼羅
釈迦如来の描き方はいろいろ。
墨絵
苦行釈迦や出山釈迦など。十六羅漢や十六善神を伴う図もあり。
彫刻
単独彫刻に立像・坐像・半跏像・倚像など。
絵画
国宝・重要文化財
独尊像
独尊像はレア。
- 釈迦如来像:正面向き。絹本著色、平安時代後期(12世紀)、神護寺(京都市右京区)旧蔵、国宝(京都国立博物館蔵)。平安末期の理想的な仏像。赤釈迦ともいい、朱衣(一面に七宝繋ぎの截金文様)を纏います。装飾の多い宝座に結跏趺坐した施無長の正面像は端麗。黄土色の肌を表した通肩姿で、二重光背の周辺には透彫金銅細工。肉身は朱線で囲んで、衣には量を加えて立体感を出しています。
- 絹本著色釈迦如来像(持鉢釈迦如来):仏飯を持った乞食姿。西教寺(滋賀県大津市)旧蔵、重要文化財(奈良国立博物館蔵)。
釈迦三尊像
釈迦如来を中尊に、普賢菩薩が象に乗り、文殊菩薩が師子に乗る三尊仏が多いです。
1面
1幅
- 絹本著色光明本尊 1幅:有形文化財・美術工芸品〔絵画〕、所有者・光用寺、所在地・大阪市淀川区西中島7→大阪市指定文化財
- 釈迦三尊像:南北朝~室町時代・14~15世紀、絹本着色、1幅、東京国立博物館蔵→文化遺産オンライン
3幅対
- 釈迦三尊図:伝顔輝筆、中国・元時代13~14世紀、絹本著色、3幅、九州国立博物館蔵→文化遺産オンライン
彫像
木造釈迦如来坐像(室生寺金堂安置)
平安時代(一部に鎌倉時代)の作品で、国宝に指定されています。
重文指定年月日は1901年03月27日、国宝指定年月日は1952年03月29日。
一木造り立像で像高は338.3cm。金堂内陣に立並ぶ5軀の中央に大きく立っています。
仏身・光背・台座とも檜材を使い、両側の肩から袖を含めた材を矧ぎ付けて内刳りがあります。
肉身は後補の漆で黒いですが、当初は全体胡粉の地色の上に彩色され、法衣の褶は翻波式の流麗な流線をつくり、流れにそって截金で更に荘厳しています。
舟後光も板のままの上に、宝相華唐草文の中に七仏を配しています。
釈迦として指定されていますが、光背に七仏薬師が控えているので、薬壺を持たない薬師如来ともいえそう。
内陣前面には鎌倉時代製作の十二神将が並んでいます。
5軀左端の十一面観音だけが同時の作品で他の像は後世のものです。
木造釈迦如来坐像(室生寺弥勒堂安置)
平安時代の作品で、国宝に指定されています。
重文指定年月日は1903年04月15日、国宝指定年月日は1952年11月22日。
平安初期の翻波式彫法の代表的彫刻です。
木造坐像で像高は105.7cm。
檜の一木造りで、手首と膝前を別木で矧ぎ付けています。
肥満した身体に纏う法衣は、幾条にもならぶ翻波の線が深く鋭く流麗に走り、裾には渦文を刻り出しています。
彩色は剥落して白っぽく見えます。頭上の螺髪・光背・台座は失われていますが、安定感のある仏像です。
釈迦曼荼羅
釈迦中心に諸尊を配した曼荼羅。
大日経説「釈迦文仏法」
方形式。
中央の釈迦は、右手が智吉祥印、左手が宝鉢印を結んでいます。「曼荼羅集」では左右とも吉祥印(説法印)。
仏前に如来鉢、右に賢瓶、後ろは錫杖、左に宝螺を蓮華上に安置して、光炎が囲っています。
陀羅尼集経「金輪仏頂像法」
空間的な表現。
赤袈裟・七宝冠の釈迦の前に金輪、宝池の周囲に四天王、前方の般若菩薩を中心に文殊菩薩と普賢菩薩、右辺に袈裟、左辺に錫杖を配置。
一切功徳荘厳王経
空間的な表現。
獅子座に坐る釈迦は説法の相をしています。
大方広曼殊室利経「曼荼羅品」
空間的な表現。
中胎に釈迦の説法相、右・観自在菩薩、左・金剛蔵菩薩と八大菩薩が図では声聞形。
宝楼閣経曼荼羅・菩提場経曼荼羅
以上の2~4は空間的な表現になっていて、釈迦中心の「経法曼荼羅」の宝楼閣経曼荼羅や菩提場経曼荼羅にも同じように表現されています。
大日経「秘密品」
釈師子曼荼羅は金剛杵を周らした中央に金剛杵、上に蓮華・鉢を配して、左右に錫杖・袈裟を置き、さらに五仏頂を配します。三味形のため詳細は不明。




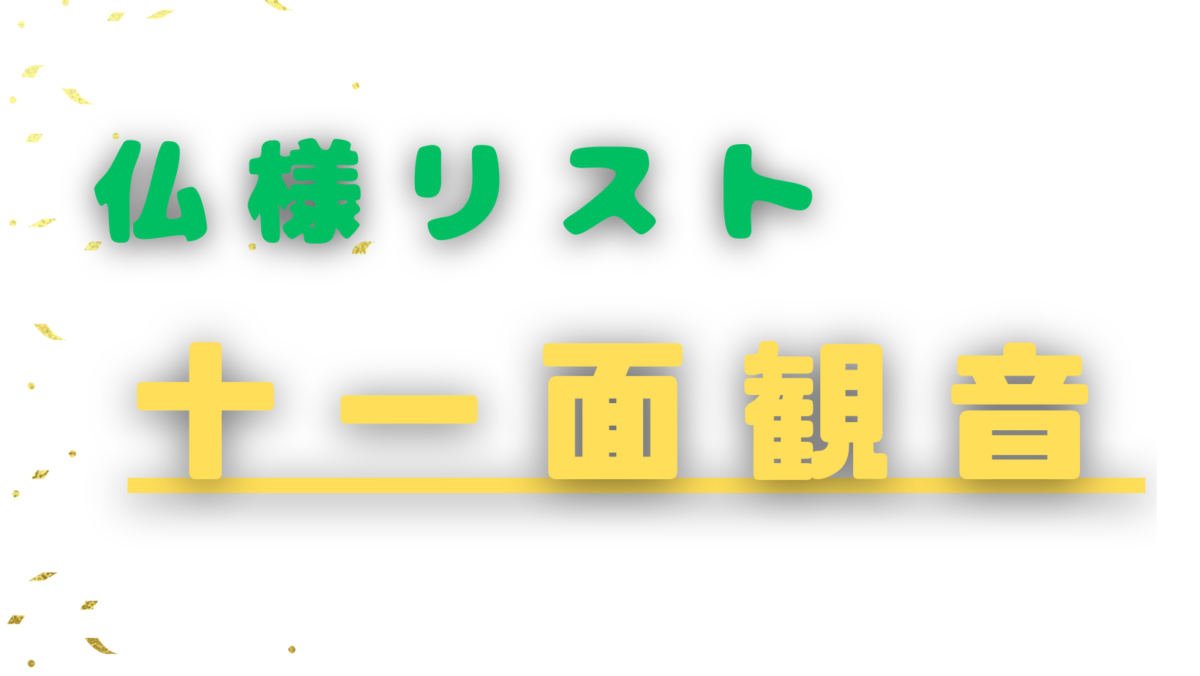
コメント お気軽に♬