
仏教で仏法を守る神。人間からだけでなく仏様たちからも信頼が厚いです。
意味
梵天とは仏教ヒエラルキーの天部に属する仏尊で、十二天(上方)の一つです。
金剛界曼荼羅では外院の二十天(東方)に住し、胎蔵界曼荼羅では外金剛部院(東方)に配属。
キャリア
インド教では毘紐天の臍から蓮華が生じ、その蓮華から梵天が誕生したという伝説にもとづいています。
もともと、バラモン教では万有創造の原 理として最高神の信仰を集めました。
さらに、密教によって天部諸神を再編成されたとき、主神として帝釈天とともに仏法守護神とされました。
日本でも密教以前から造像され、中国服の正装立像が基本形。
形姿
一面二臂
荷葉座に坐ります。
身体は肉色。
左手を拳にして腰に当て、右手は腰に当てながら蓮華を所持。
三面二臂
胎蔵旧図様に登場。
鵝の背に乗っています。
左手に蓮華を所持し、右手は与願印を結んでいます。
三面四臂
胎蔵図像に登場。
鳥の背に坐っています。
右の上手に数珠を、下手に彎刀を、左の上手に蓮華を、下手に瓶を所持。
四面四臂
現図曼荼羅に登場。
蓮華座に坐します。
四面すべて菩薩形で各面三目。
右手は掌を仰げて与願印風に結んでいます。次手で鉾を立てます。
左手は肘を曲げて掌を立て、開敷蓮華を持ち、次手は下げて操瓶を所持。
外院中で蓮華座に坐るのはこの仏尊だけです。
「図像鈔」では3羽の鵝に乗る図。
「大日経疏」には、髪髻冠を付け、七鵝車に坐し、右手に蓮華・数珠を持ち、左手は軍持を所持して、字印を結んでいます。
東寺講堂の木造像では、4鵝が、車座に外を向いた共通の胴に蓮台を置いて、蓮台の外へ右足をはみ出した女性的肥満像。中面のみが三目で、左手に蓮華・鉾・払子を所持し、右手は突き出して掌を見せ、別の手に戟を所持。
文化財
日本では密教以前から造像され、中国服の正装立像が基本形です。
東大寺法華堂、法隆寺食堂、唐招提寺金堂などに安置されています。
密教像は、東寺講堂の四面四臂像で白鵝に乗る像が典型(先述)。
乾漆〈梵天/帝釈天〉立像
2軀。国宝。
- 乾漆〈梵天/帝釈天〉立像
- 彫刻 / 奈良時代
- 重文指定年月日:19010802
- 国宝指定年月日:19520328
- 東大寺法華堂安置
- 国宝・重要文化財(美術品)
本尊の二重八角仏壇の外側に、それぞれ八角形の板2枚を重ねた簡素な台座に立つ巨像です。
身に付いた鎧の上に法衣を纏い、梵天は経巻を持って、帝釈天は前に袈裟を垂れています。
奈良仏教は顕教的な性格によって明るく支配されていて、雑密の輸入によって、仏像表現に影響が徐々に現われています。
写実本意の内面性を表出するにいたり、少し密教の世界に近づいています。
ことに法華堂全体が、顕教では見られない神秘的な内容を含み、次代への過渡期に入ろうとしています。
梵天・帝釈天立像
- 国宝 奈良時代(8世紀)
- 木造・乾漆併用 彩色
- 唐招提寺・金堂
巨大な本尊の前に並んで、四隅の四天王像と近い高さで、主尊の3巨像を囲んでいます。
檜材の一木造り。部分的には乾漆材で成形してから仕上げています。
木心乾漆造から一木彫への過渡期の作。
鎧の上に法衣を纏うのは東大寺法華堂と同じ。
台座の反花の上面に人物・馬・兎・蛙・ 唐草などの戯画戯書が発見され、奈良時代の絵画史料を提供しています。
→木彫
木造天部立像
- 大阪市指定文化財
- 分野/部門:有形文化財/美術工芸品〔彫刻〕
- 所有者:宗教法人 浄円寺
- 所在地:大阪市淀川区新北野3




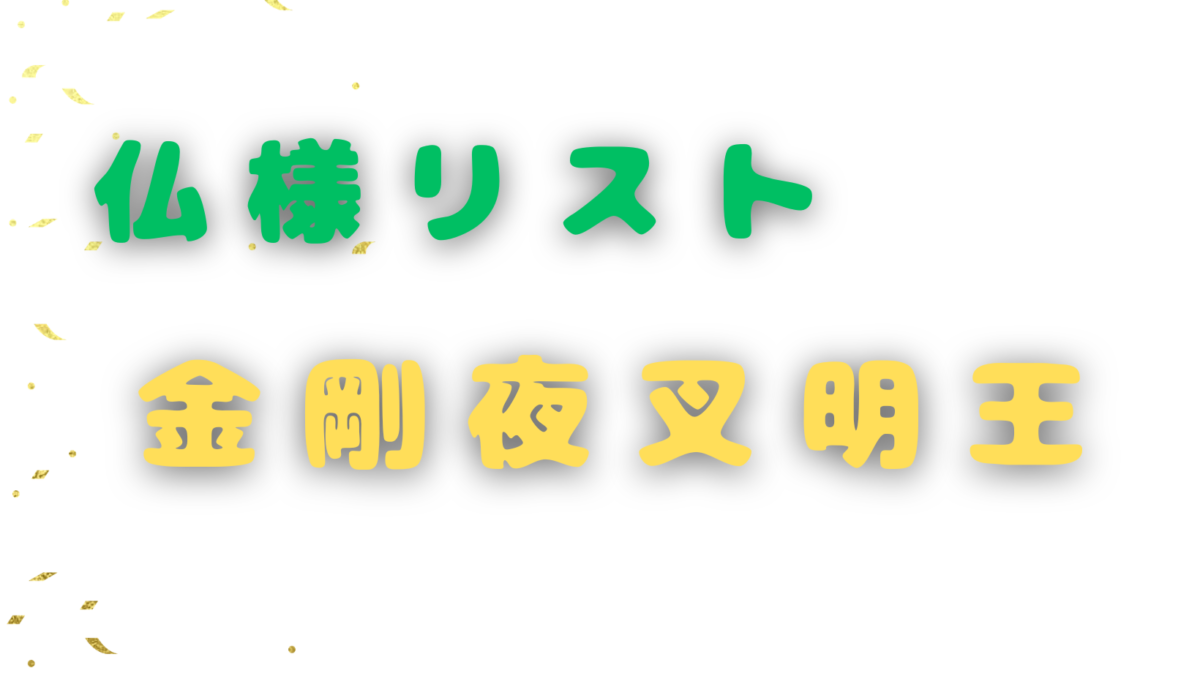
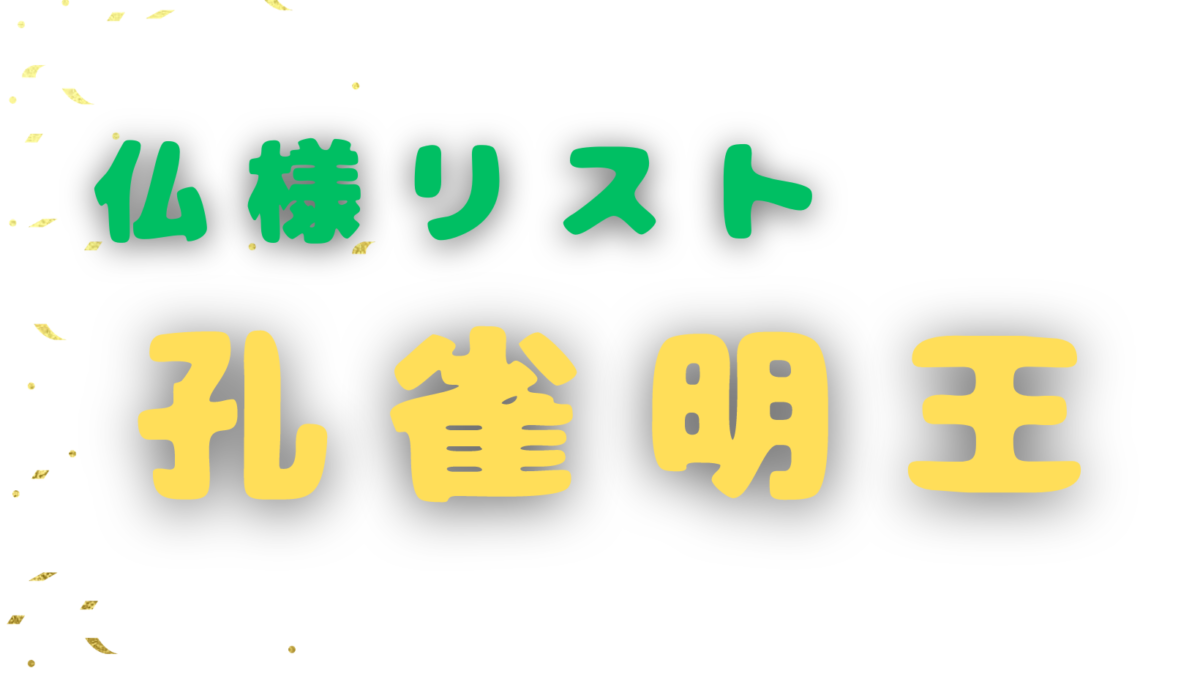
コメント お気軽に♬