六祖の風幡論(心の真実)
唐の時代、広東の新州に貧しい樵(きこり)の子・慧能(えのう)がいました。字も知らず、ただ薪を売り母を養う日々。ある日、市場で客が『金剛経』を朗読する声を聞き、突然、心が澄み渡った。「應無所住而生其心(応に住すること無かれ而して其の心を生ぜよ)」——その一節に打たれ、慧能は出家を決意。黄梅山の五祖・弘忍のもとへ向かった。
寺では雑役を命じられ、八ヶ月間、臼で米を突く。弘忍は後継を決めるため、弟子たちに偈(げ)——詩を詠ませた。筆頭の神秀は夜中に壁に書いた:
身は菩提樹
心は鏡台のごとし
時時に勤めて払拭せよ
塵埃をして染むこと勿れ
「心を磨き続ける努力」を説いた。慧能はこれを聞き、別の偈を詠んだ:
菩提 本来 樹なし
鏡も亦 台にあらず
本来 無一物
何れの処にか塵埃を惹く
「本来的に清浄、何を払う必要があるか」。弘忍は慧能の偈を読み、夜中に密かに法を授け、衣鉢を継がせた。神秀は驚き、追手を放ったが、慧能は山を越え、追っ手を振り切り、南方へ逃れた。
十五年後、広州の法性寺で慧能は剃髪。壇経を説き、「自性自度」——外の仏ではなく、自分の心が仏だと教えた。ある日、風が幡(ばん)を揺らすのを見て、二人の僧が論じた。「風が動く」「幡が動く」。慧能は笑って言った。「風でも幡でもない。汝らの心が動いている。」
この「風幡論」は、現象は心の投影だと示す。風も幡も実在するが、「動く」と見るのは心の分別。慧能は「無念無相無住」を説き、南宗禅の祖となった。
『六祖壇経』に記されるこの話は、禅の「頓悟」を象徴。神秀の「漸修」に対し、慧能は「一瞬の悟り」。現代では、完璧主義の罠に似る。SNSで「磨く」投稿を繰り返すより、慧能のように「本来清浄」と気づけば、ストレスは消える。慧能は無学だったが、経の一節で目覚めた。私たちも、日常の小さな声——鳥のさえずり、子どもの笑い——に耳を澄ませば、そこに法がある。風幡論は、「見る者が変われば世界が変わる」という、静かな革命の宣言だ。



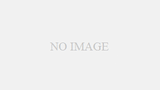
コメント お気軽に♬