達磨の壁観九年(禅の静寂)
中国・南北朝時代、梁の武帝は仏教を篤く信仰し、寺を建て経を写しました。インドから船で渡来した達磨(だるま)は、皇帝に謁見を許されました。武帝は誇らしげに問うた。「朕は数多の寺を建立し、僧に施しをした。どれほどの功徳があるか?」達磨は静かに答えた。「功徳なし。」皇帝は驚き、「なぜだ?」達磨は言った。「それは有為(うい)の行為。真の功徳は無相(むそう)——形なきものにこそある。」
武帝は理解できず、達磨を遠ざけました。達磨は長江を渡り、北魏へ向かい、嵩山少林寺の洞窟に入りました。そこに座り、壁に向かって九年間、黙して動かず。風雪が吹き、獣が吠えても、ただ壁を見つめました。村人は「狂った坊主」と噂し、子供が石を投げても、達磨は瞑目したまま。
九年目の冬、雪深い夜、一人の若者・神光(後の二祖慧可)が洞窟前に立った。達磨の教えを求めて山を越え、凍える足で雪に埋もれながらも、「心が不安で死にそうです。どうか法を説いてください」と叫んだ。達磨は振り返らず、「真の法は言葉にあらず。雪の中で己を滅せ。」神光は剣を抜き、左腕を切り落とし、血の滴る腕を差し出した。「これが私の求道の証です!」
達磨は初めて振り向き、静かに言った。「お前の心は、いつ私の心と一つになった?」神光は悟り、涙を流した。「求めていた心が、すでにない。」達磨は頷き、「それが安心(あんじん)だ。」これが禅の「直指人心、見性成仏」——言葉を超え、心で心を伝える始まりでした。
この話は『景徳伝灯録』などに記され、中国禅宗の開祖・達磨の伝説です。壁観は「坐禅」の極致。外の壁は内なる妄想の鏡。九年は象徴で、一瞬の決断を表します。武帝の「功徳」は形ある善行、達磨の「無功徳」は執着なき自然な行い。神光の断臂は、自己を捨てる覚悟——「我」を切ることで「法」が入る。
現代では、情報洪水の中で「壁観」はスマホを置く一時を意味します。通知を切り、ただ呼吸を見つめる。達磨は「不立文字」——経典より体験を重んじました。私たちも、スクロールを止め、目の前の壁(現実)と向き合えば、静寂の中に答えがある。達磨の赤い顔は怒りではなく、燃える求道心。九年の果てに伝えたのは、「お前がすでに仏だ」というシンプルな事実。このエピソードは、禅の「喝!」——一撃で目覚める、静かなる革命です。(約998文字)




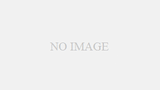
コメント お気軽に♬